
こんにちは!京大電気電子工学科で勉強している電電ボーイです!今回は2回生前期の時間割を紹介していこうと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 電気電子工学科の時間割ってどんなの?
- 電気電子工学科ってブラックって聞くけど本当なの?
- 2回生前期の時間割がわからなくて困っている
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そんな人の疑問に今回は答えていこうと思います。ただし、大学の時間割は人によって違うので、時間割を組む際は学部や学科の履修要覧等を確認の上取りたい授業を取るようにしましょう。
時間割の全体像
まず、これが2回生前期の時間割の一例です。あくまで一例であり、単位数や興味によって時間割は多少変わってくるのでご注意ください。

ゴリゴリに難しそうなものばかりですよね、、、特に水曜と木曜に演習があり大変そうです。それでは曜日ごとに詳しく見てきましょう。
月曜日
月曜日は2限、確率論基礎からのスタートです。確率論基礎では期待値や確率分布といった統計力学や量子力学でも使われている確率論の基礎を学びます。この授業は履修登録の際デフォルトで入っており自分で入れたわけではないです。京大工学部では履修登録の際、学部や学科でとることが推奨されている科目があり、その科目の多くは自分で入れなくてもデフォルトで時間割に入っています。そのため特段時間割をいじらなくても1,2回生は何とかなります。
話を戻します。成績評価も先生によってかなり変わってくるのでシラバスで確認するようにしましょう。三浦先生の確率論基礎は中間レポート50%、期末テスト50%で決まりました。中間レポートは標準的な難易度でしたが、期末テストは教科書やノートが持ち込み可だった分難しかったです。
3限は哲学です。僕は一般教養科目の人社群の単位があと2単位足りなかったので哲学をこの時間に入れました。松本先生の哲学は出席40%、授業の最後にある小レポート50%、期末レポート10%で評価されます。つまり毎週遅刻せずに出席し、授業の最後にちょっとしたレポートをかいていれば単位をもらえます。
4限は熱力学です。森成先生の熱力学はわかりやすい上に単位取得も比較的容易なので本当にお勧めです。成績は基本的に期末試験100%で決まります。しかし筆者のときはなぜかオンライン小テスト50%、中間レポート50%でした。
5限は微分積分学続論Ⅰ-ベクトル解析です。この授業では電磁気学を学ぶ上で必ず必要になるベクトル解析を学びます。伊藤先生のベクトル解析は基本的に期末試験100%ですが、7月くらいの授業中に問題演習があり、その演習での出来や、中間レポートで多少下駄をはかせてくれます。
火曜日
火曜日は1限からのスタートです。まずは物性・デバイス基礎論です。この授業では量子力学と統計力学の基礎を前半で学びその後物性(熱伝導や電気伝導等)について学びます。なかなか盛りだくさんな科目です。基本的に期末テスト100%で決まります。下駄はありません。また採点もかなり厳しいため落とす人もかなり多い印象です。院試にも出るため履修することをお勧めしますが、落としてしまってもあまり気にしなくて大丈夫です。
2限は関数論です。この授業では複素関数について学びます。複素関数は機械制御等電気電子工学の広い分野で用いられているため重要科目です。基本的に期末試験100%で決まります。萩原先生の関数論では下駄はありませんでした。しかし授業資料に過去問がたくさん載っているためそれを使って勉強すれば単位を取得することができます!頑張ってください。
4限は線形代数学続論です。この授業では対角化やジョルダン標準形、エルミート形式など1回生の線形代数では習わなかったことを学びます。基本的に期末試験100%で評価されますが、木坂先生の線形代数は中間レポートがあり多少下駄をはかせてくれます。また木坂先生の過去問はありませんがレポートの問題をしっかり理解して解けるようになっておけば試験も大丈夫です。
水曜日
水曜日は4限からのスタートです。遅いですね。筆者は水曜の午前中にバイトを入れていました。
4,5限は電気電子プログラミング演習です。この授業ではC言語について学びます。成績は授業中の課題50%、最終課題50%で決まります。授業ではほとんどC言語についての演習です。授業中に課題はすべて終わります。最終課題は0から9までの白黒で書かれた数字を読み取るニューラルネットワークの作成です。この最終課題の詳細は第一回の授業からすでに授業資料に掲載されているのでプログラミングが得意な方は早めに終わらせておくと後々すごく楽になります。口頭試問もあるので他人のコードの丸写しは禁物です。困ったらChat GPTやGeminiに助けてもらいましょう。
木曜日
木曜日は3限からのスタートです。3,4限に必修の電気電子回路演習があります。遅刻厳禁で3時間ひたすら班員と課題をするのでしんどいですが、必修なので頑張りましょう。課題はほとんどすべてその回のテーマに沿った発展課題を班で設定し、実験や解析をするという内容です。また、全ての回で事前課題があります。それに加え2,3週間に1回レポートがあります。内容は設定した発展課題のうち1つを深く掘り下げるものとなっています。そして最後には発表課題があり、班で1つアナログ回路を用いて面白いものを作るというものです。筆者はギターのエフェクタを作りました。結構面倒くさいですが頑張りましょう。
金曜日
金曜日は1限からのスタートです。1限は論理回路です。この授業では論理回路(AND, OR, NAND等)について学びます。成績は基本的に期末試験100%です。橋本先生はほとんど毎授業簡単な課題を下駄として出してくれる上に加点課題もあります。期末試験対策用の問題集も渡してくれるのでそれらを使ってしっかり勉強すれば単位を必ず取得できます。
2限は電子回路です。この授業ではトランジスタやオペアンプを用いたアナログ回路について学びます。成績は基本的に期末試験100%で決まります。杉山先生は各章ごとで教科書の問題を解いて提出すれば下駄として少し加味してくれます。しかしその教科書の問題にはとんでもなく難しいものもあります。そのような問題は試験にも出ないので解かなくても大丈夫です。また、過去問も授業資料に豊富にあるのでそれらを解いていればしっかり単位を取得できるはずです。
まとめ
2回生からゴリゴリ理系科目が始まり試験勉強もつらくなってきます。しかし最低限のことを普段からやっておくだけでその試験勉強は各段に楽になります。もう2回生なんだとあきらめてちょっとだけ頑張りましょう。

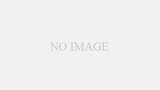
コメント